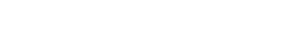つづれ織の知恵袋
石川つづれ株式会社の爪掻本つづれ織にまつわる「よもやま話」をブログで紹介していきます
-
2025.05.09
-
2024.03.10
-
2024.02.22
【日本文化継承プロジェクト「狼煙 -NOROSHI-」】に掲載いただきました。
「爪掻本つづれ織をもっと多くの人に知ってもらいたい」という思いと
次世代に伝統をつなぐために、
この技術を守り続けることが私の使命であると感じています。
そんな気持ちをインタビューで
お答えしました。
ぜひこちらのサイトをご覧ください。
【「狼煙 -NOROSHI-」インタビューページ】
https://noroshiofficial.com/interview/2025-5-7/
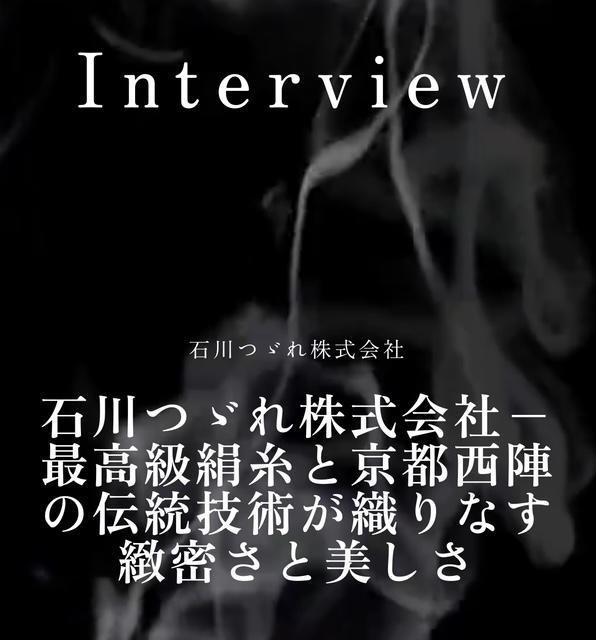
【西陣爪搔本つづれ織】織機説明「踏木)について
つづれ織機(つづれおりき)は、布地を織るための道具。踏木(ふみき)は、織機の下部にある足で踏んで操作する部分を指します。踏木を踏むことで、織機の糸を織り上げるための動きを作り出します。踏木の数や配置は、織りたい模様や織り方によって異なる場合もあります。踏木の操作は、綜絖に連動しており織機の糸が上下に動き、布地や模様が作られます。織物の織り方をコントロールするために、踏木の使い方には熟練した技術が必要です。
#つづれ織り#綴れ#これからも織り手の技術の継承や新たなデザインの開発に取り組んでいきます#綴れ#綴れ織りの帯 #伝統工芸 #石川つづれ #西陣
西陣爪掻本つづれ織の魅力を伝えるために、私たちはこれからも織り手の技術の継承や新たなデザインの開発に取り組んでいきます。西陣織の伝統を守りながらも、時代のニーズに応える織物を生み出すことで、継続した発展を目指しています。